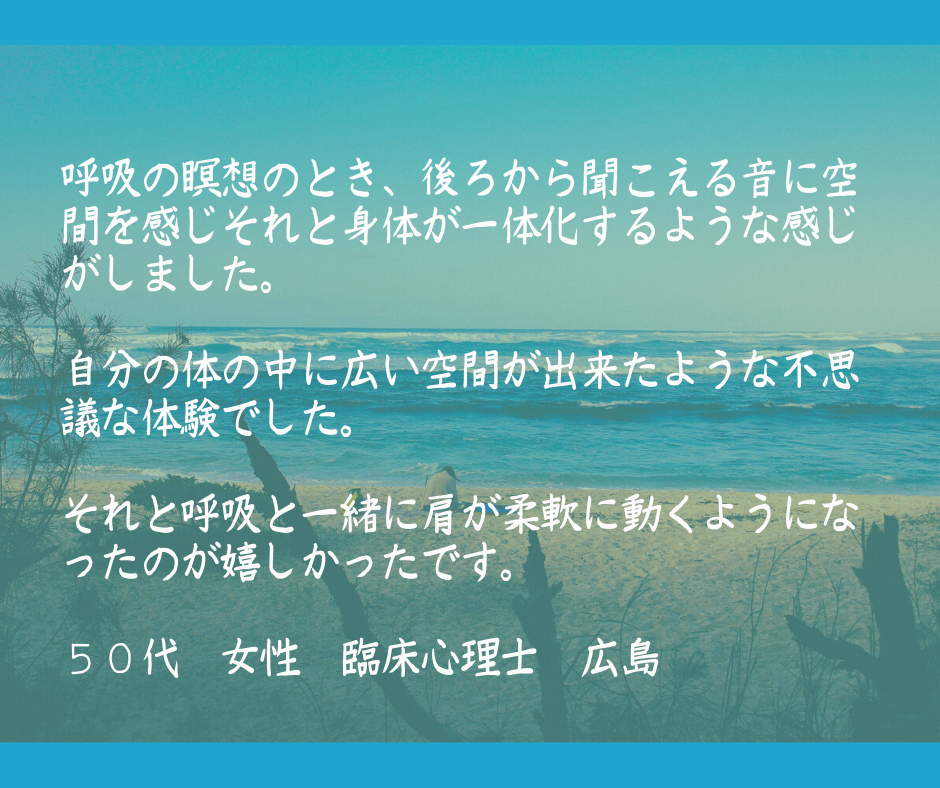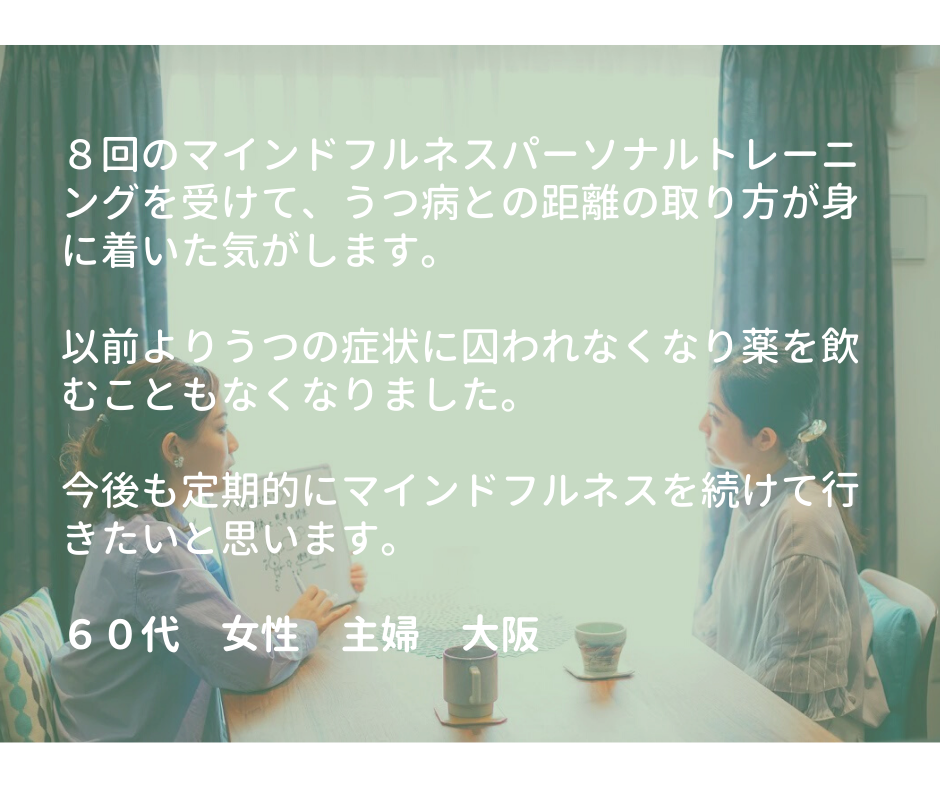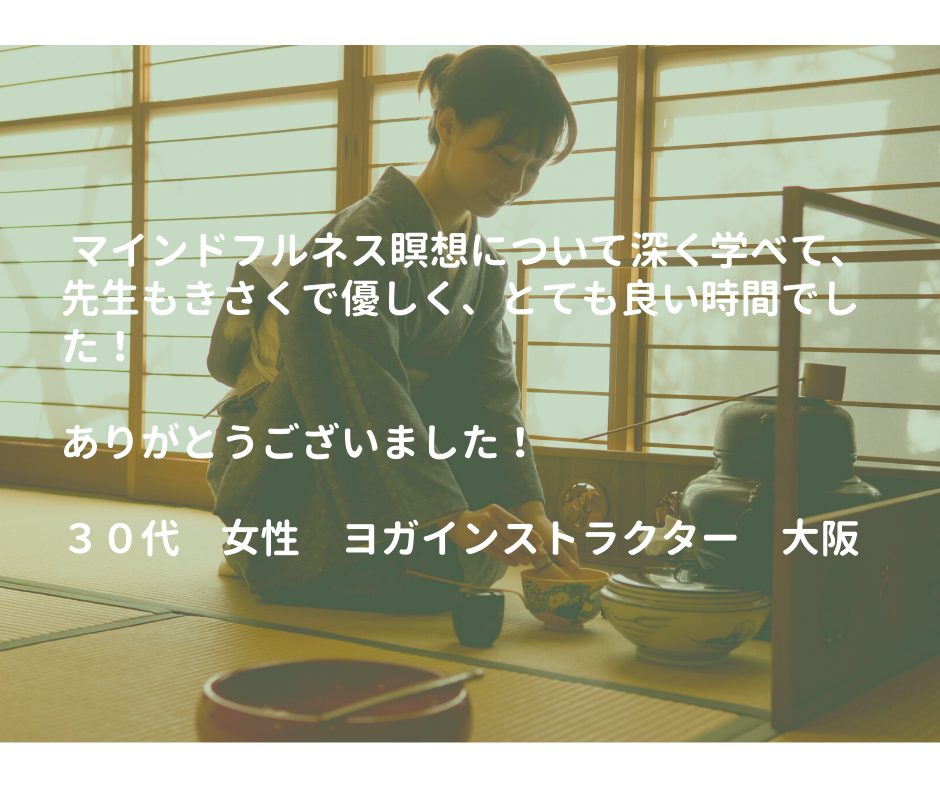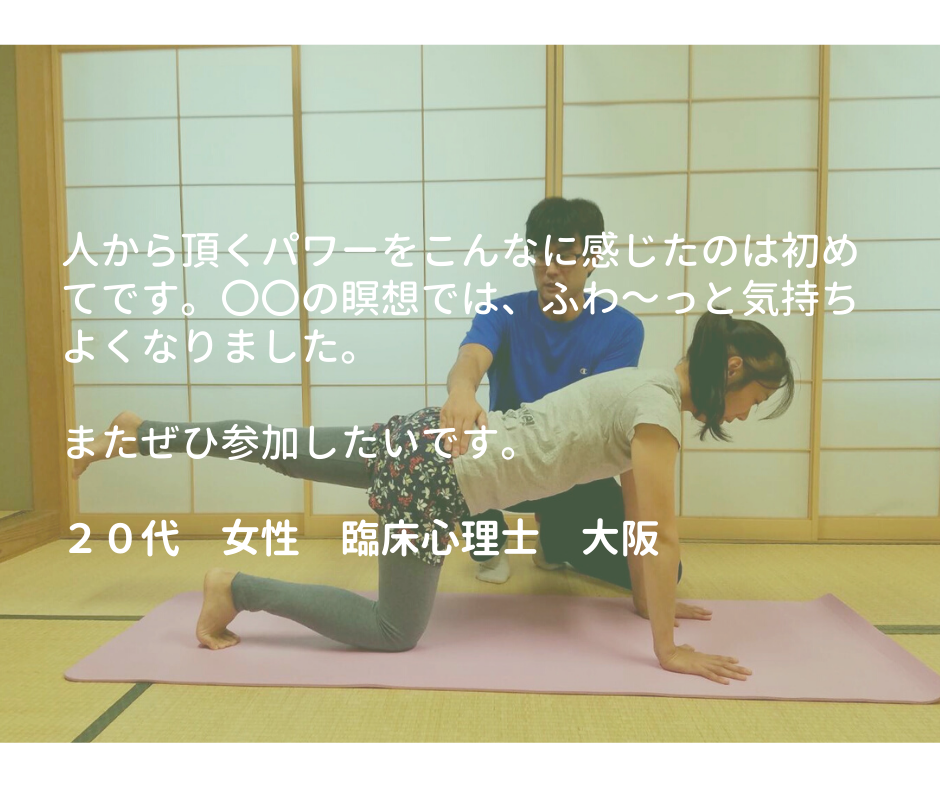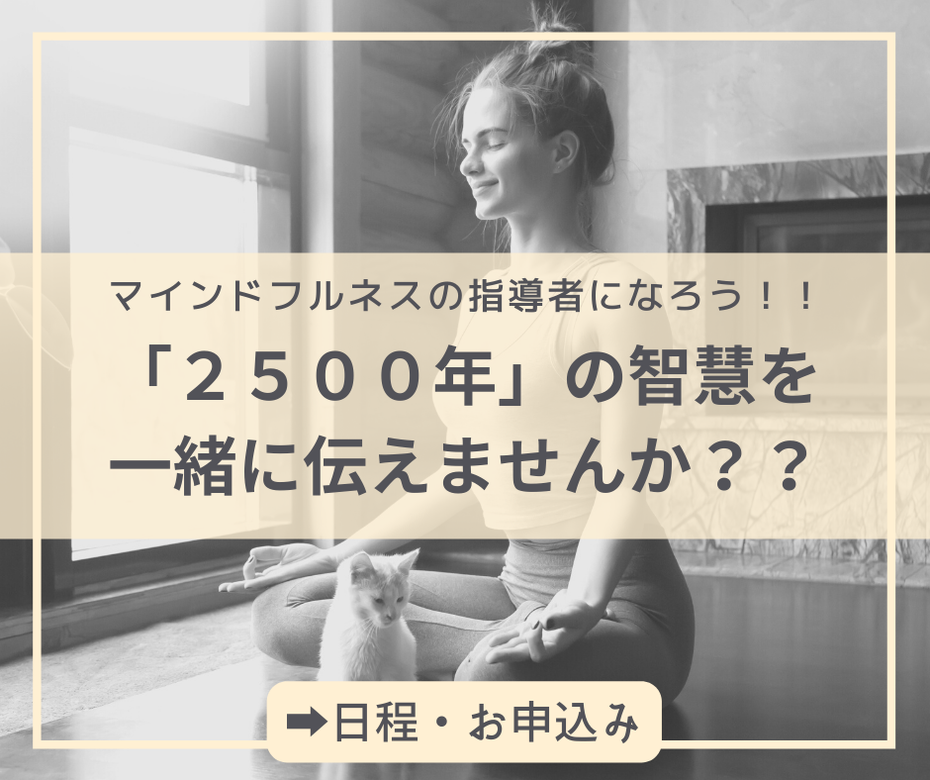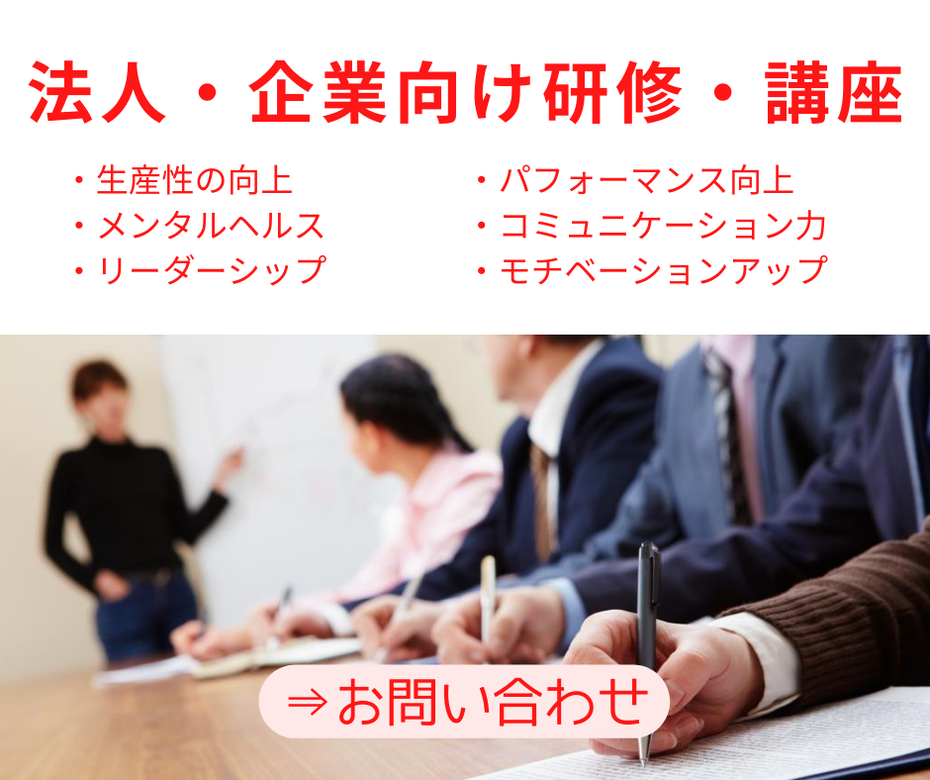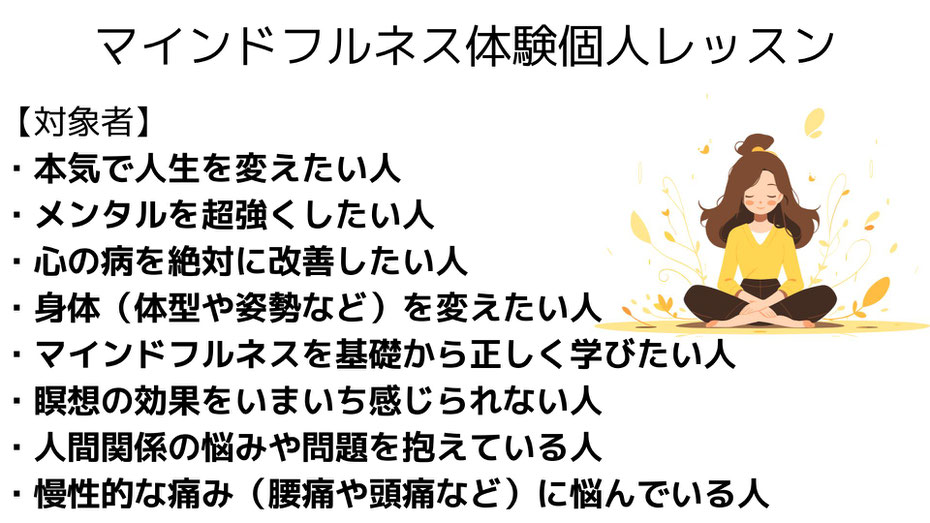

あなたが人生を歩む上での最強の武器は、私たち全員が持っている心(脳)です。
スマホでもパソコンでもネットでもAIでもありません。
流行りのAIに聞いても自分の人生の答えは出てきません。
家族や友人、カウンセラーはサポートしてくれるかもしれませんが
人生の決断や責任は自分一人で取らなければいけません。
私たちは一人です。
お釈迦さまも「自分以外を拠り所にしてはいけない(自灯明)」という言葉を残しています。
本当に辛いとき、苦しいときに頼れるのは自分の心(脳)です。
最終的に頼れるのは、自分の心(脳)だけです。
マインドフルネスの瞑想や実践は、その心(脳)を上手く使うため、鍛えるための方法です。
「心地良くなる」「心を落ち着かせる」「現実逃避」「嫌な気持ちを消す」
といったリラクゼーションではありません。
マインドフルネスの瞑想や実践は、極めて科学的で再現性があります。
つまり正しい方法で継続すれば、誰でも心(脳)の使い方が上手くなり、強くすることが可能なのです。
本気でレッスンで提供する内容に取り組めば
・人生が大きく変わります。
・常に穏やかで居ることが出来ます。
・メンタルが超強くなります。
・感情に振り回されなくなります。
・集中力が段違いに上がります。
・頭が賢くなります。
・圧倒的な情報処理能力が身に着きます。
・人間関係が良好になります。
・好かれる人間になります。
・健康状態が改善します。
・あらゆる病気の予防につながります。
・目覚めや寝つきが良くなります。
・自信や自己肯定感が高まります。
・幸福感が高まります。
・自然に無駄な体重が落ちます。
これ本当です。一切の誇張はありません。
大阪マインドフルネス研究所は
どこの宗教団体や政治団体とも関係しておりません。
物販やネットワークビジネスもしていないため
HPに記載されているレッスン費以外を請求することはありません。
受講者の声
脳の機能と構造が変わる
マインドフルネスの瞑想や実践に継続して取り組むと
脳の機能と構造に変化が生じることがわかりました。
脳科学の発展によって主観的な体験や意見だった瞑想の効果に
科学的な根拠があることが明らかになったのです!!
脳が物理的にも発達することから「脳の筋トレ」と呼ぶ人もいます。
このような研究結果によって
マインドフルネスは様々な分野へ応用が可能であることもわかりました。
欧米では医療分野を中心に「福祉」「教育」「ビジネス」「スポーツ」
などの分野にも導入されて一定の成果を上げています。
日本では女子刑務所や少年院にも更生プログラムとして
正式にマインドフルネスが導入されています。
厚生労働省と文部科学省もマインドフルネスを推奨。
独学での実践は危険
大阪マインドフルネス研究所では「ネット」「アプリ」「書籍」
などの情報を元に独学でマインドフルネスに取り組むことをお勧めしていません。
理由は次の5つです。
①間違って行うと精神のバランスが崩れる。
②間違って行うと精神疾患が悪化するリスクがある。
③間違って行うと性格が悪くなることがある。
④独学での実践では効果を得ることが非常に困難。
⑤フィードバックがない状態では、習得が不可能。
より詳しく知りたい方
↓ ↓ ↓
精神疾患を抱えている人は、絶対に自己流で取り組んではいけません!!
マインドフルネスの瞑想や実践に取り組みたいと望む方には
マインドフルネス個人レッスンをお勧めしています。
まずは体験レッスンからどうぞ。
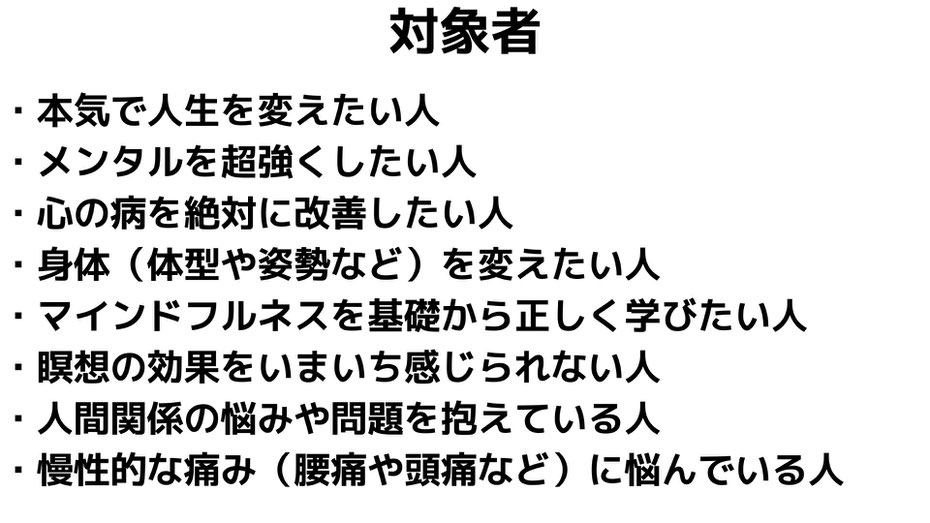


体験個人レッスン
【日程】
完全予約制となっております。
【料金】
初回 60分:10,000円
【指導者】
大阪マインドフルネス研究所
代表 西山純一 詳しいプロフィール⇒こちら
【場所】
大阪 天満橋駅より徒歩3分
*お申し込みの方にご案内させて頂きます。
受講希望の方は
下記のメールフォームにてお申込みください。
料金のお支払い方法
料金のお支払いは
「銀行振り込み」「当日現金でのお支払い」「クレジットカードでのお支払い(ペイパル)」の3つを選んで頂けます。
前日、当日のキャンセルにつきましてはキャンセル料金(全額)が発生しますのでご注意ください。
こちらからお申込みください

*メール送信後、24時間以内に返信がない場合はお手数ですが
mindfulness-lab①nifty.com までメールをお送りください。
①を@に変更して送信してください。お願い致します。
延べ参加人数1000人超えのマインドフルネスセミナーです。
マインドフルネスや瞑想を1から学び、実践しようと望むあなたにお勧めします!!
もちろん中・上級者にも有益な内容。
このセミナーや講座に参加すればあなたが抱えている問題は解決し
今後の人生を大きく変えること間違いなしです!!
ぜひご参加ください!!
オンラインでの1日マインドフルネス講座も実施しています。
こちらの講座は1日でマインドフルネスの
基本的な理論と実技をキッチリ習得する内容となっております!!
・マインドフルネスを学びたいが時間がない方
・大阪に来ることが難しい方
・新型コロナウイルス感染の不安がある方
・自宅で簡単に学びたい方
におススメの講座です。
大阪マインドフルネス研究所では
マインドフルネスの指導者を養成するための講座を行っております。
当研究所が主宰する指導者養成プログラムはマンツーマンでの個別講座となっております。
講座をマンツーマンで行う理由は
優秀な指導者を送り出したいという気持ちが強いからです。
一般的な講座は、複数人が参加するグループレッスン形式で行われています。
この形式のデメリットは1人1人の理解度や習熟度を考慮できない点です。
複数人が参加する講座では時間の都合上
1人1人に寄り添った内容で進めることが困難です。
このような形ではどうしても受講者の理解や習熟に差が出てしまいます。
他の参加者に遠慮して気軽に質問することも出来ません。
マンツーマンであれば理解度や習熟度を考慮し
1人1人に寄り添った内容で講座を進めていけます。
納得するまでいくらでも質問することも出来ます。
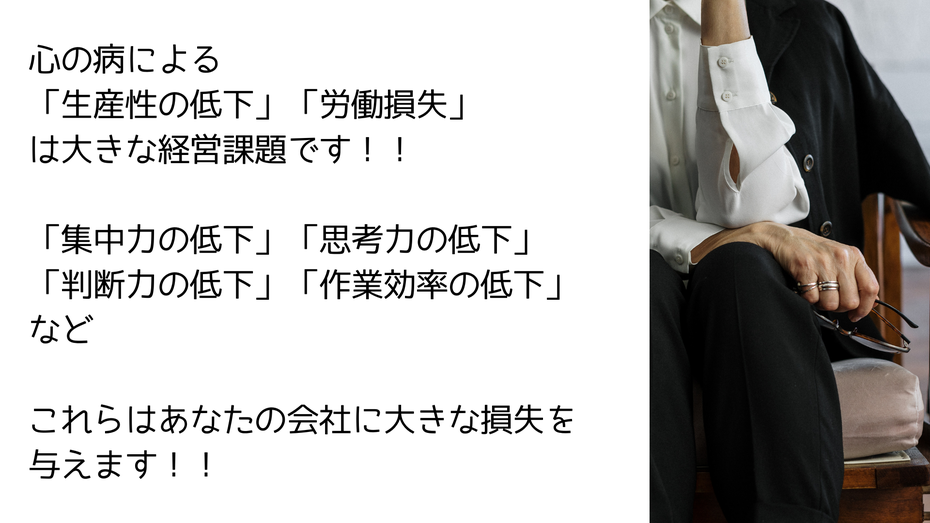
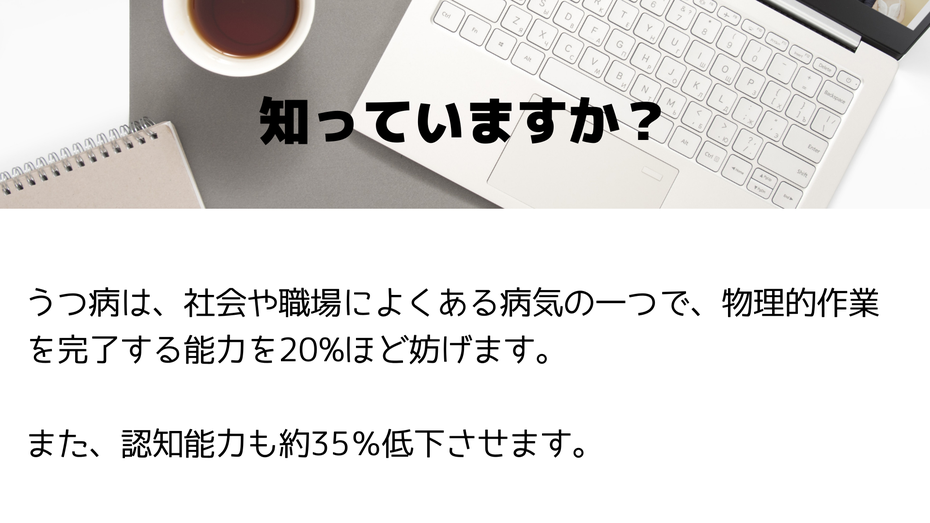
当研究所では、法人や企業向けの研修や講座も実施しております。
【期待できる効果】
・IQ(思考力や判断力、記憶力や集中力など)の向上
・メンタルヘルス(ストレス耐性向上)
・創造性、直観や感性の向上
・コミュニケーション力向上・共感力アップ
・リーダーシップの向上
・ビジネスパフォーマンスの向上
・ストレス軽減
・モチベーションアップ
など
【導入している主な企業】
Google、ゴールドマンサックス、Facebook、P&G、インテル、Yahoo、資生堂、トヨタ、イトーキ
リクルート、パナソニック、メルカリなど何百社が導入。
京セラの創業者である稲盛和夫氏、appleの故スティーブジョブス氏
パナソニックの故松下幸之助氏を始め
多くの経営者やビジネスマンもマインドフルネスの実践や瞑想経験者。
【マインドフルネスを導入した結果】
・半年間で利益が倍以上にアップ
・うつ病を患う従業員が40%減少
・平凡な営業マンが売り上げ全国2位を達成
・生産性の向上→残業時間が65%減少
・従業員の71%がストレス軽減を実感
・上司と部下のコミュニケーションの問題が解決
・社長のゴルフスコアが伸びた
など
クチコミ
慢性腰痛を改善
慢性腰痛とはMRIやCTで検査しても異常がないのに腰の痛みが3か月続くことを言います。
近年、慢性腰痛は腰ではなく脳に原因があることがわかってきました。
脳にアプローチしなければ、薬や注射、手術を行っても痛みが消えないのです。
2015年7月12日放送のNHKのスペシャル番組内でも紹介されています。ご確認ください。
指導者の選び方!
指導者を選ぶ方法として有効な質問があります。
- 実践経験はどれくらい?
- 自身の変化について教えて?
- どこで?誰に習ったのか?
- これまで何人の人に指導してきたか?
- その中でどれくらいの人に変化があったか?
- どれくらいで効果が現れるのか?
- 「マインドフルネス」と「瞑想」の違いは?
- 「呼吸瞑想」と「呼吸法」の違いは?
- マインドフルネスの危険性を教えて?
- うつ病の人も取り組んで大丈夫?
これらの質問にきちんとした答えが返ってくるようであれば指導者として信頼できる可能性が高いでしょう。
問い合わせの際にメールで質問してもいいかもしれません。